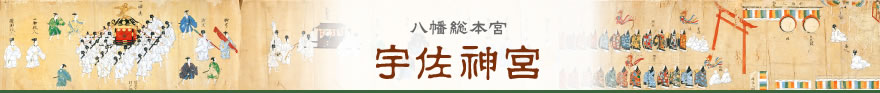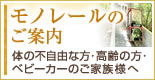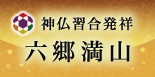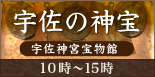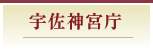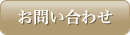7月 行事予定
「夏越大祭」「夏祭」「ごじんじ」等と呼ばれ多くの方々に親しまれていますが、正式には「宇佐神宮御神幸祭(ごしんこうさい)」と称します。古くは「御祓会(おはらいえ)」とも呼ばれ、人々の疫病を除き災厄を防ぐと共に、八幡総本宮として国家国民の安寧を祈願する祭礼です。
この祭典の歴史は古く、宇佐神宮の根本史料である『八幡宇佐宮御託宣集』によると、平安時代の嘉承元~3(1106~08)年より以前に始まったとされています。
御本殿より御神体が神輿に遷り、御仮屋である境内の頓宮(とんぐう)まで御神幸されます。
頓宮で三日二夜を過ごされた後、再び上宮御本殿へと御還幸されます。
神幸行列は、天狗のように赤く鼻高の猿田彦神が道案内として先頭に立ち、鮮やかな色彩の装束をまとった「蝶」「鳥」「駒(馬)」の稚児が列を成します。続いて裃(かみしも)や直垂(ひたたれ)を着けた列奉行、太鼓・横笛・鉦を賑やかに奏でる道行囃子、三基の神輿の後ろに宮司と神職が従います。まさに時代絵巻さながらの光景が繰り広げられます。
7月31日(木)
午後 3時 本殿祭・御発輦祭(ごはつれんさい)
午後 5時半頃 菅貫神事(すがぬきしんじ)①
宮司以下神職は頓宮北側の斎庭にて「菅貫神事(すがぬきしんじ)」を行います。「解縄串(ときなわぐし)」という宇佐神宮古儀による祓具にて神職全員が自祓を行った後、正面に立てられた三本の川御幣(清らかな流れを表す)に一人ずつ静かに進み、拝礼の中で最も丁寧な作法である「起拝」の後に、解縄串を川御幣に向かって投げ入れ、国家安泰・万民息災が祈念されます。

①菅貫神事
8月1日(金)
午前10時 式日祭・流鏑馬神事本殿奉告祭
午後 3時 流鏑馬行列進発・奉幣神事②
午後 4時 流鏑馬本義③
御神幸祭中日には、天下泰平・五穀豊穣・悪疫退散を祈念する「流鏑馬神事」が斎行されます。当日は鎌倉時代より続く流派「小笠原流」の方々が弓を引き、鎌倉時代の狩装束を着装し奉仕します。

②奉幣神事

③流鏑馬本義
8月2日(土)
午後 3時半 御還幸祭
午後 8時 厄除花火大会④
厄除・疫病退散を祈念する花火大会を催します。
スターマインなど約1,000発を打ち上げ、御神幸祭の締め括りを彩ります。

④厄除花火大会
御田植祭
午後3時 斎行(本殿祭)
鳥羽天皇の保安四(1123)年に始まったと伝えられている五穀豊穣の予祝儀礼です。
上宮での祭祀終了後、宮司以下はひし形池の池畔に設けられた小さな水田の斎場へ向かい、御田植神事を斎行します。
水守が斎田に水を注ぎ鍬を担いで斎田を三巡、その後に郷司が水守を従えて田を一巡します。神職による雅楽が奏でられる中、紺がすりの筒袖に、赤い腰巻と襷(たすき)をかけ、花笠をかぶって田の神に扮した少女(早乙女)たちが、斎田を三巡しつつ早苗を斎田へ放ちます。

御田植祭(斎田祭)の様子
夏越の大祓
午後4時 斎行
大祓は毎年6月30日及び12月31日に斎行されます。
大祓とは、知らず知らずのうちに犯したであろう自らと社会の罪穢れを、形代を用い祓い去り心身を清める神事です。
6月30日に斎行される大祓は「夏越(なごし)の大祓」と称され、酷暑の季節を迎えるに当たり、更なる気持ちで今後の生活を過ごしていくための神事です。
解縄串(ときなわぐし)・切麻・裂布等といった特殊な祓具を用い、神職を始め参列者、全国各地の崇敬者より送られた形代(かたしろ)をお祓いします。
形代とは、ご本人の身の代として罪穢れを受ける祓具であり、祓い後は神職により、寄藻川(よりもがわ)へ流します。
また古式に則り「茅の輪」が参道に設けられます。
水無月の 夏越しの祓へする人は
千歳の命 延ぶと言ふなり
拾遺和歌集に詠まれるこの和歌を歌いながら茅の輪をくぐると、無病息災で残る半年を過ごすことができるといわれています。
<夏越の大祓参列をご希望の方>
当日午後3時45分までに、神宮庁手水舎前受付にお越しください。
初穂料は1,000円以上お志しのお納めとなります。
※遠方等の事情により参列の困難な方は、宇佐神宮へご一報ください。形代及び案内状をご送付申し上げます。
宇佐神宮 TEL:0978-37-0001

祭典後は茅の輪をくぐります
虫振祭 / 風除祭
「虫振祭(むしふりさい)」・「風除祭(ふうじょさい)」ともに、毎年6月に斎行される「御田植祭」に関わる重要な祭典です。
「虫振祭」とは、かつて御殿内の装束及び宝物類である能衣装関係・面・文書等の虫干しを行う祭礼でしたが、後に転じてイナゴやウンカなどの水田の病害虫の災いの無い様に祈念する神事となります。
また、同日には「風除祭」が斎行されます。台風などの風水害から被害を受けやすい8月の時期に、稲や農作物の安全な生長を祈念する神事です。
旧宇佐町戦没者慰霊祭
境内大尾山裾野に、143柱の旧宇佐町出身の護国英霊を祀る「英霊之碑(忠魂碑)」が鎮座しています。
先の大戦における戦没者を追悼し、恒久平和を祈念するため、終戦記念日である8月15日にこの碑前において祭典を斎行します。
水分神社例祭
水分神社(みくまりじんじゃ)は菱形池の小島に鎮座し、水を司る五柱の神様をお祀りしています。
水分神社例祭は毎年8月28日に斎行され、氏子崇敬者が参列し、稲の成長を祈念します。
7月 行事予定
「夏越大祭」「夏祭」「ごじんじ」等と呼ばれ多くの方々に親しまれていますが、正式には「宇佐神宮御神幸祭(ごしんこうさい)」と称します。古くは「御祓会(おはらいえ)」とも呼ばれ、人々の疫病を除き災厄を防ぐと共に、八幡総本宮として国家国民の安寧を祈願する祭礼です。
この祭典の歴史は古く、宇佐神宮の根本史料である『八幡宇佐宮御託宣集』によると、平安時代の嘉承元~3(1106~08)年より以前に始まったとされています。
御本殿より御神体が神輿に遷り、御仮屋である境内の頓宮(とんぐう)まで御神幸されます。
頓宮で三日二夜を過ごされた後、再び上宮御本殿へと御還幸されます。
神幸行列は、天狗のように赤く鼻高の猿田彦神が道案内として先頭に立ち、鮮やかな色彩の装束をまとった「蝶」「鳥」「駒(馬)」の稚児が列を成します。続いて裃(かみしも)や直垂(ひたたれ)を着けた列奉行、太鼓・横笛・鉦を賑やかに奏でる道行囃子、三基の神輿の後ろに宮司と神職が従います。まさに時代絵巻さながらの光景が繰り広げられます。
7月31日(木)
午後 3時 本殿祭・御発輦祭(ごはつれんさい)
午後 5時半頃 菅貫神事(すがぬきしんじ)①
宮司以下神職は頓宮北側の斎庭にて「菅貫神事(すがぬきしんじ)」を行います。「解縄串(ときなわぐし)」という宇佐神宮古儀による祓具にて神職全員が自祓を行った後、正面に立てられた三本の川御幣(清らかな流れを表す)に一人ずつ静かに進み、拝礼の中で最も丁寧な作法である「起拝」の後に、解縄串を川御幣に向かって投げ入れ、国家安泰・万民息災が祈念されます。

①菅貫神事
8月1日(金)
午前10時 式日祭・流鏑馬神事本殿奉告祭
午後 3時 流鏑馬行列進発・奉幣神事②
午後 4時 流鏑馬本義③
御神幸祭中日には、天下泰平・五穀豊穣・悪疫退散を祈念する「流鏑馬神事」が斎行されます。当日は鎌倉時代より続く流派「小笠原流」の方々が弓を引き、鎌倉時代の狩装束を着装し奉仕します。

②奉幣神事

③流鏑馬本義
8月2日(土)
午後 3時半 御還幸祭
午後 8時 厄除花火大会④
厄除・疫病退散を祈念する花火大会を催します。
スターマインなど約1,000発を打ち上げ、御神幸祭の締め括りを彩ります。

④厄除花火大会