
大昔に鬼がいて、『人を喰べていいか』と神に許しをこうたところ、大神は、『わが宮の石段百段を一夜に築いたならば許してやろう』と言われました。鬼は懸命に石段を積みましたが、99段目まで積み上げたとき、大神は、鶏を鳴かせて夜が明けたと告げられました。鬼は原(はる)の蛇堀の池に身を投げたといいます。これは百段にまつわる伝説です。昭和造営前の石段は大石を使った荒造りでした。

上宮の裏、菱形池のほとりに三つの霊泉があります。御霊水(ごれいすい)、または御鍛冶場(おかじば)、下井の霊水とも言い、八幡大神が御現れになったところであるとされています。ここには八角の影向石(ようごうぜき)があり大神が神馬に召され、天翔けられたと伝えられる馬蹄の跡があります。また、奈良朝の末ごろ、社僧の神息(しんそく)が御霊水の前に三個の井戸を掘り、この水で八幡大神の神威を頂いて刀を鍛えました。これが社宝となっている『神息の刀』と伝えられています。
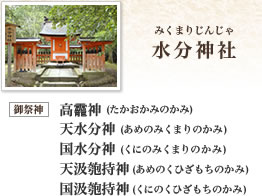
水を司る五神を祀る神社です。菱形池、御霊水前の小島に鎮座され、中島の竜宮様とも申し上げます。

七月末、八月上旬毎年行われる神幸祭に、三日二夜の間御滞在になる御旅所(おたびじょ)に当る社殿です。昭和御造営に臨み、大鳥居の外側にあった社殿を応永年間の頓宮旧蹟に復されました。昔の造替の時の上宮、下宮、若宮の頓宮は、当時の各社殿に準じ、大きな規模であったことが古図に残っています。
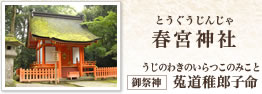
応神天皇の御子神で、勉学に励み寵愛されていましたが、兄の大鷦鷯命に皇太子の座を譲りました。学問の神としてご守護くださいます。
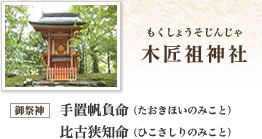
宮大工・寺大工・桧皮師・塗師の職人達と、近郷近住の職人の守護神です。
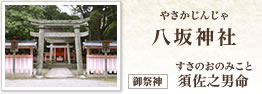
須佐之男命(すさのおのみこと)をお祀りしています。この神社の西側に昔の神宮寺弥勒寺の金堂や講堂の旧蹟があります。この神社の前で、毎年二月十三日に鎮疫祭(ちんえきさい)が行われます。
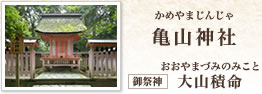
上宮が鎮座している小椋山(おぐらやま)は亀山といいます。亀山神社は、亀山の山の神である大山積命(おおやまづみのみこと)を祀る神社です。

八幡大神の八王子神をお祀りしております。社殿の構えはなく、上宮、西回廊の楠の木に鎮まっておられます。

天平勝宝元年(749)八幡大神は比売大神とともに奈良に行幸、天平勝宝7年(755)伊予の宇和に移り、10年後奈多宮を経由して宇佐に御帰還になりました。その時、宇佐三山の一つ大尾山の頂上に御鎮座するとの託宣があったので、天平神護元年(765)に造営し、八幡大神様はここに約15年御鎮座されました。この間の神護景雲3年(769)7月11日、和気清麻呂公が弓削道鏡の事件に際して勅使として参拝され、八幡大神様より国体擁護の御神教を授かった霊地です。
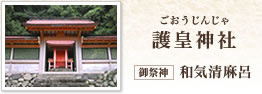
道鏡事件の際、八幡大神様の神託を受けて国の危機を救った和気清麻呂をお祀りしています。

宇佐神宮の神域を流れる川で、源は御許山の南にあり、流れの末端は、古くから放生会を行っている和間の浜で、周防灘に注いでいます。寄藻川は、この川の総称で、呉橋から川上を寄藻川、また呉橋川といい、呉橋から表参道の神橋までを月瀬川、表参道神橋から神社の境域付近を浅瀬川といい、場所によって名が変わります。 『古事記』、『日本書紀』にある『菟狭の川上』はここのことで、寄藻川沿岸はいろいろな史蹟に富んでいます。
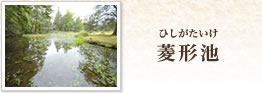
欽明天皇三十二年、八幡大神が御現われになった霊池です。その名の所以は宇佐の三山、菱形にかこまれているため。古くから霊池として有名です。

参集殿・宝物館との間に隣接しているこの池は、奈良の猿沢(さるさわ)の池、京都の広沢(ひろさわ)の池と並ぶ日本三沢の池として古くから有名です。7月〜8月にかけて古代蓮が美しく咲きます。
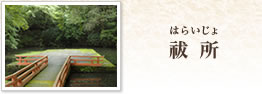
勅使奉幣祭をはじめ大祓式などの祭典の祓の儀を行う所です。この前の広場を古くより御輿掛(おこしかけ)と称し、宮司の輿を倚するところです。
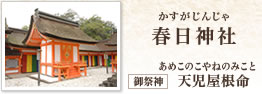
一之御殿、八幡大神の脇殿です。ご祭神の天児屋根命(あめのこやねのみこと)は春日大明神とも言われ、神功皇后をお助けになった尊神です。
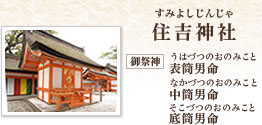
三之御殿、神功皇后の脇殿。神功皇后に数々のご神威を与えられた住吉大神を弘仁14年(823年)よりお祭りしています。
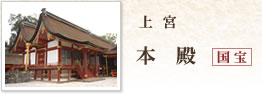
宇佐神宮の建築様式は八幡造(はちまんづくり)とよばれています。奥殿を「内院」・前殿を「外院」といいます。内院には御帳台があり、外院には御椅子が置かれ、いずれも御神座となっています。御帳台は神様の夜のご座所であり、椅子は昼のご座所と考えられています。

下宮の八幡大神は、御饌(みけ)を司るとともに、農業や一般産業の発展、充実をお守りになるご神威を発揮されます。古くから日常の祭祀には、とくに国民一般の祈願や報賽(ほうさい)が行われてきました。

応神天皇の若宮であられる大鷦鷯命(仁徳天皇)と皇子をお祀りしています。除災難・厄難の神様として有名です。

鎌倉時代より以前からある西参道の屋根がついた神橋です。昔、呉の国の人が掛けたともいわれ、この名があります。

神宮内郭の南正門。高良大明神、阿蘇大明神の二神を御門の神としてお祀りしています。

比売大神の脇殿といわれ、本宮の地主神と伝えられる造化三神を祀っています。上宮西中門の中に鎮座しています。

文禄のころ(1592〜)改築されたといわれ、国宝の本殿、勅使門などと共に宇佐神宮の景観を象徴する建物です。

宇佐古来の形式をもつもので、額束(がくづか)はなく、台輪を柱上に置いています。宇佐の鳥居の規格となるものです。

祭器具等を納める高倉の板倉です。前面のみ持送りで縁を設け、擬宝珠(ぎぼし)高欄を備えています。
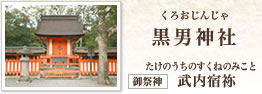
武内宿祢は、景行天皇、成務天皇、仲哀天皇、応神天皇、仁徳天皇と、五代の天皇に二百四十余年もの間大臣として仕えたと伝えられます。数多くの功労があり、忠誠を尽くされたことをもってお祀りされています。八幡大神にご奉仕された神であり、古くから大鳥居の外に鎮座になって大神をお護りされています。長寿、忠誠、奉仕などの高いご神徳を授けられます。